八味地黄丸(はちみじおうがん)とはどういう漢方薬?尿トラブルに効くって本当?

年齢を重ねると、男女問わず、これまで考えもしなかった身体の不調に悩まされることがあります。
尿のトラブルもそのひとつです。特に男性は、年齢を重ねるにつれて膀胱の筋肉が弱まって、頻尿や夜間尿などになりやすくなります。
一方、女性は男性に比べて尿道が短いため「咳やくしゃみをしたときに、尿がもれてしまった」「トイレに行くまでに間に合わず下着を汚してしまった」という経験がある人も少なくありません。
尿トラブルがあると、トイレが不安になって、外出するのが億劫になりがちです。しかし、デリケートな問題なので、多くの人が誰にも相談できず困っています。
1人で悩んだり、お出かけを控えたりする前に、ぜひお試しいただきたいのが「八味地黄丸(はちみじおうがん)」。
中高年の尿トラブルに効果的な漢方薬です。ここでは、八味地黄丸の情報についてお届けします。早めに対策をとって、はつらつとした人生を送りましょう。
八味地黄丸(はちみじおうがん)とは

医薬品「八味地黄丸」は、中国の医書『金匱要略(きんきようりゃく)』にも記載されている漢方薬です。まずは、八味地黄丸がどのようなお薬なのかを簡単にご紹介します。
八味地黄丸は8種類の生薬をハチミツで練り合わせた丸剤です。
別名「腎気丸(じんきがん)」とも呼ばれるように、腎の機能を高める働きがあり、新陳代謝機能を高めて、中高年以降の尿トラブルのお悩みを改善していきます。
身体を温め、身体全体の機能低下をもとに戻していく
八味地黄丸は、身体を温めて、加齢によって低下した全身の機能低下をもとに戻していく処方です。
冷えに伴う痛みを取る際に用いられる「附子剤(ぶしざい)」のひとつに数えられます。
「気」「血」「水」を増やし巡らせる生薬と、身体を温める生薬を組み合わせることで、頻尿や軽い尿もれ、夜間尿、残尿感などを改善していきます。
また、身体を温めることによって、足腰などの慢性的な痛みやしびれなど、中高年によくみられる症状の改善を図ります。
「腎虚(じんきょ)」に対して用いられている
漢方でいう腎とは、現代医学でいう腎臓だけを指すものではありません。
成長や発育、生殖を司る副腎、膀胱、そして生殖器などの機能を総じて腎と呼びます。
漢方では衰えた部分を「虚」といい、「腎虚」は加齢によって腎の機能が低下もしくは不足した状態です。
八味地黄丸には、腎の働きを良くする生薬を主薬に、8種類の生薬が配合されています。
腎の衰えを補って、新陳代謝機能を高める働きがあり、中年以降の保健薬・治療薬としての効果が期待できます。
西洋薬と違う点
西洋医学では、膀胱炎に対しては、菌を殺すための抗菌剤や炎症を抑えるための抗炎症剤を使い治療をするのが一般的です。
また、尿量減少に対しては尿を出やすくする薬を、頻尿に対しては尿を出にくくする薬を使って治療します。
しかし、それらは症状をとるだけの対症療法にすぎず、根本的な治療にはなりません。
一方、漢方では、頻尿や尿もれといった表面的な症状ではなく、その原因に働きかける治療をします。
同一の薬で、頻尿にも尿量減少にも対応できるのはそのためです。
自然治癒力を引き出して、体質自体を改善し、根本的な治癒を目指します。
漢方は、原則として自然界にある植物や動物、鉱物を複数組み合わせて作られるお薬です。
八味地黄丸はどんな人に向いている?

漢方薬は、人によって向き・不向きがあります。
適切に使うには、まず自分に向いているかどうかを確認することが大切です。八味地黄丸は次のような人に向いています。
体力があまりなく、疲れやすく、四肢が冷え、尿量が多いもしくは少ない人
八味地黄丸は、漢方でいうところの「虚証」「腎虚」「寒証」「臍下不仁(さいかふじん)」の人に向いています。
「証」とは、病気に対する抵抗力や心身のあり方をあらわす漢方独自の「ものさし」です。
「虚証」とは、本来あったものが失われた空虚な状態です。身体の線が細く、青白い顔をして疲れやすい、いわゆる「虚弱体質」の人は虚証に分類されます。
すぐ風邪を引いてしまう、冷え性や腰痛、低血圧といった症状に悩まされているのもこのタイプです。
「腎虚」は前述したとおり、泌尿生殖器や下半身の衰えがみられる人です。
さまざまな尿トラブルは、この腎虚による症状と考えられます。
頻尿によってトイレが心配で高速道路に乗れない、尿意が我慢できない、会議中でもトイレに駆け込んでしまう人は、腎虚タイプといえるでしょう。
また、残尿感や排尿困難を感じている人や、夜間尿の人も当てはまります。
「寒証」の人は、手足などの局所が冷えている状態です。頻尿で下痢を起こすことも多いでしょう。
尿の色が透明もしくは薄く、量が多い場合は、身体の冷えによるものと考えられます。
上半身に比べて下腹部が脱力して抵抗力がない状態を、漢方では「臍下不仁」といいます。
足腰の弱い人や高齢者によくみられるタイプです。
おへそから下の部分がふにゃふにゃして緊張感がない場合は、八味地黄丸を用いるひとつの目安になります。
そもそも「尿トラブル」の原因は?
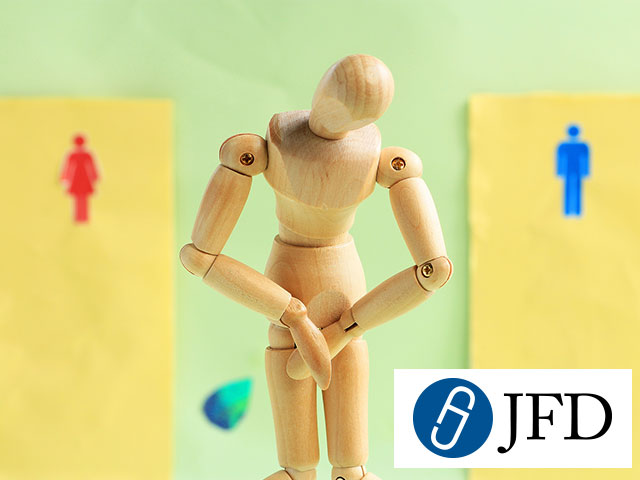
八味地黄丸はさまざまな「尿トラブル」に効きますが、そもそも「尿トラブル」はなぜ起こってしまうのでしょうか。その理由をご説明します。
「気・血・水」は加齢によって失われていく
漢方医学では、人の身体は「気(き)・血(けつ)・水(すい)」の3つからできていると考えられています。
「気」とは目に見えないが人の身体を支えるすべての原動力のようなもののことです。
それに対して「血」は全身の組織や器官に栄養を与えるもの、「水」は食べ物や飲み物に含まれる水分を消化吸収によって人体に必要な形にして身体をうるおすものを意味しています。
西洋医学では心と身体を分けて考え、身体についてはさらに臓器・器官ごとに細かく分類し、病気にアプローチしていきます。
一方、漢方医学の場合は、心と身体をひとつと捉えて、病気は心身のバランスが崩れることで起こると考えるのが特徴です。
「気・血・水」が加齢によって失われてしまうと、身体のうるおいや温かみをつくり出せず、身体が乾いて冷え、柔軟性が損なわれてしまいます。
それらを補い、バランスを整えるのが漢方薬の役割です。
尿もれや頻尿の原因に
尿もれや頻尿といった尿トラブルは、身体の機能低下とともにうるおいや温かみが失われ、膀胱やその周りの筋肉(暴行排尿筋)の柔軟性が低下することで起こります。
わかりやすく例えると、柔軟性のあるゴムの袋はよく伸びるため、ある程度無理してもたくさんのものが詰められます。
しかし、硬い素材の袋は柔軟性がないので、あまり多くのものを詰め込むことはできません。
尿トラブルを抱えた膀胱は、柔軟性がなく、硬く伸びない袋のようなものです。
そのため、やわらかく伸びる健康な膀胱に比べると、蓄えられる尿の量がどうしても少なくなってしまいます。
また、温かみが失われた身体は冷えやすく、汗をかきにくいので、水分が外に逃げていかず、ほとんどが尿に回ります。
しかし、膀胱排尿筋が衰えて尿をたくさん溜めることができないため、トイレに行く回数が増えてしまうことに。
その結果、何度もトイレに行きたくなる、尿もれ、夜間尿などの症状に見舞われるのです。
八味地黄丸の効能効果
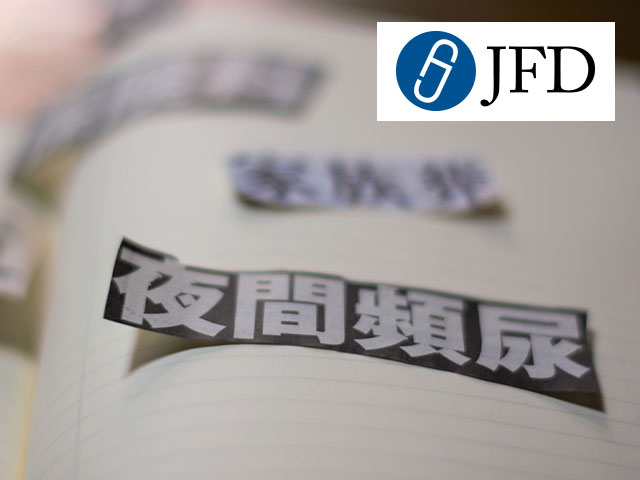
八味地黄丸は、その名のとおり8種類の生薬が配合されており、身体を温め、全身の機能低下をもとに戻していく処方になっています。具体的には次のような症状に効果的です。
頻尿・夜間頻尿
「さっきトイレに行ったばかりなのに、また行きたい」「夜中に何度もトイレに起きる」という人は、頻尿・夜間頻尿の可能性があります。
頻尿・夜間頻尿は、身体が冷えて尿が溜まりやすいのに加えて、膀胱の柔軟性が失われることで起こる症状です。
八味地黄丸は身体を温めて、巡りを良くすることで頻尿や夜間尿を改善していきます。
残尿感・排尿困難
「排尿したあとも、尿が残っている感じがする」「なかなか尿が出ない」といった現象は、中高年によくみられる症状で、膀胱の血行不良や老化現象が原因で起こると考えられます。
50歳以上の男性の場合、肥大した前立腺が膀胱を刺激することによって引き起こされるケースも多いようです。
八味地黄丸は血行を促して、腎の働きを元気にすることで症状の緩和を図ります。
軽い尿もれ
尿もれにはいくつかの種類がありますが、咳やくしゃみをしたときなどに少量尿がもれるのは、加齢などによって尿道を支える筋肉の衰えたのが原因と考えられます。
軽い尿もれは女性に多い症状で、40歳以上の4割が経験しているというデータもあります。
八味地黄丸は生薬の働きで、腎の機能を回復させ、下半身の衰えに伴う尿もれを改善します。
高齢者のかすみ目
中高年になると、目のかすみや視力低下を訴える人が増えてきます。
かすみ目は、漢方医学的には、かすみ目を身体の栄養素である「血」が不足した「血虚」の状態であると捉えています。
漢方薬の中で、不足した血を補う代表的なものが、八味地黄丸です。
あわせて、レバーやほうれん草など血を補う食材を積極的にとることをおすすめします。
下肢痛、腰痛、しびれ、かゆみ、むくみ
身体の機能低下による不調は、尿トラブルだけではありません。
下肢のしびれや痛み、腰痛などの症状を自覚する人も増えていきます。
八味地黄丸はこうした足腰の痛みや倦怠感の治療薬としても効果的です。
飲み続けることで、下半身の不安が減り、元気に活動できるようになります。
高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)
血圧が高いと、随伴症状として肩こりや頭重、耳鳴りといった症状が起こることがあります。
八味地黄丸は高血圧の治療を主たる目的とした漢方薬ではありませんが、身体を温めて血流を改善し、血圧を安定させることで、高血圧に伴う肩こりや頭の重み、耳鳴りなどを改善する効果が期待できます。
八味地黄丸の使用上の注意

八味地黄丸は医薬品ですので、用法用量を守って服用していただく必要があります。
ここでは、八味地黄丸の用法用量や使用上の注意などについて、詳しくご説明します。
用法・用量
15歳以上の成人の場合、1回20丸を1日3回朝昼夕、食前または食間に水またはお湯でかまずに服用します。
ちなみに食間とは、食事と食事の間を意味するもので、食後約2~3時間のことです。
7歳以上15歳未満の場合は、1回14丸を1日3回服用します。なお、7歳未満は服用しないでください。
使用上の注意(してはいけないこと)
八味地黄丸はその名が示すとおり、地黄を中心とした8種類の生薬が配合されています。
地黄は下痢や胃痛、胃もたれなどの胃腸障害を起こす可能性があるため、胃腸の弱い人や下痢しやすい人、胃薬を常用している人は服用を控えてください。
お薬はたくさん飲んだからといって、効果が高まるものではありません。かえって身体に負担をかけてしまいます。用法・用量を守って、正しくお使いください。
もし飲み忘れたとしても、2回分を1度に服用するのは厳禁です。規定量をオーバーして、副作用が起こるリスクが高まります。
たとえば朝に飲み忘れたら、その分はパスして、昼から通常どおり服用するようにしましょう。服用のタイミングを決めておくと、飲み忘れ防止に役立ちます。
使用上の注意(服用前に相談すること)
以下の事項に当てはまる方は、本剤を服用する前に医師や薬剤師にご相談ください。
- 医師の治療を受けている人
- 妊婦または妊娠していると思われる人
- のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
- 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどを起こしたことがある人
併用を禁じられている薬は特に指定されていませんが、医薬品と一緒に服用される場合は、身体に負担をかける可能性も考えられるため、念のため、医師、薬剤師もしくは登録販売者にご相談されることをおすすめします。
1ヶ月以上服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、添付文書を持って、医師、薬剤師もしくは登録販売者にご相談ください。
保管及び取り扱いに関する注意
直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
お子様が誤って服用することがないよう、小児の手の届かないところ、見えないところに保管しましょう。
また、他の容器に詰め替えるのはお控えください。誤用を招いたり、品質が変わったりする可能性があります。
食べ物に消費期限や賞味期限があるように、薬にも使用期限があります。
期限の切れたものは、変質していたり、効能が落ちていたりすることがあるので、余った分は服用せずに処分しましょう。
なお、この場合の使用期限とは、未開封で適切に保管している状態での期限です。
開封後は使用期限にかかわらず、早めにご使用ください。
八味地黄丸の副作用

八味地黄丸は医薬品ですので「副作用の可能性がまったくない」とは断言できません。
以下で、副作用として起こりやすい症状についてお伝えします。
八味地黄丸を服用して、まれに次のような症状が出る場合があります。
このような症状に気づいたら、ただちに使用を中止し、当ページや商品販売ページを医師、薬剤師もしくは登録販売者に見せてご相談ください。
副作用の可能性があるもの
皮膚:発疹・発赤、かゆみ
生薬によるアレルギー反応で、身体に発疹が出現したり、皮膚が赤く腫れたり、かゆくなったりする場合があります。
これまでに同様の皮膚症状が起こったことがある方は、あらかじめ医師や薬剤師にご相談ください。
消化器:食欲不振、胃部不快感、腹痛、下痢
地黄が配合されている漢方薬は、胃に負担をかけることがあります。
胃もたれや下痢などの副作用がよくみられるため、胃腸の弱い方は注意が必要です。
その他:動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ
八味地黄丸は、血や熱の量が不足している人に用いられる漢方薬です。
血と熱を補って、身体を温める作用があるため、一部からは動悸やのぼせ、舌のしびれ感などの副作用が報告されています。
もともと暑がりでのぼせがある方は、副作用が起こりやすいため、避けた方が無難です。
八味地黄丸に含まれる生薬

八味地黄丸には、腎の働きを良くする8種類の生薬が配合されています。
漢方についての基本的な知識を押さえたうえで、それぞれの特徴についてみていきましょう。
漢方医学には、西洋医学にはない、陰陽五行説に基づいた独自の考え方があります。
生薬を組み合わせるときに、5つの性質をあらわす「五性」と5つの味をあらわす「五味」を指標とするのが特徴です。
五性とは、生薬を摂取したときの熱寒性を「寒・涼・平・温・熱」の5つに分類してあらわしたものです。
身体を冷やす寒涼性のもの、身体を温める温熱性のもの、どちらでもない平性のものが存在します。
冷えによる痛みなどの「寒証」には温熱性の薬を、ほてりやのぼせなどの「熱証」には温熱性の薬を用いるのが基本です。
これを『以寒治熱、以熱治寒(寒を以って熱を治し、熱を以って寒を治す)』といい、漢方薬による治療の原則です。
それに対して、五味は「酸」「苦」「甘」「辛」「鹹(かん)」の5つの味を意味しています。
順に「酸っぱい・苦い・甘い・辛い・塩辛い」をあらわしたものです。それぞれの味には効能効果があり、特定の臓器と密接な関係にあると考えられています。
生薬が五臓(心・肝・脾・肺・腎)のうちどの部分に作用するのかを示したのが「帰経(きけい)」です。
いずれも生薬を処方する際に有用な手がかりとなります。
八味地黄丸は、腎に効く「ジオウ」「サンシュユ」「サンヤク」「タクシャ」「ブクリョウ」「ボタンピ」「ケイヒ」「ブシ末」をバランス良く配合。
新陳代謝を高める働きがあり、中高年の保健薬・治療薬としてご活用いただけます。
ジオウ(地黄)
ゴマノハグサ科アカヤジオウ、カイケイジオウの根を乾燥したものです。
日本には平安時代に中国から伝わり、古くから薬草として親しまれてきました。
生の状態の「鮮地黄」、乾燥させた「乾地黄」、酒蒸しして乾燥させた「熟地黄」などの種類があり、加工法により効能が異なります。
五性:微温。五味:甘。帰経:肝・脾。
サンシュユ(山茱萸)
ミズキ科サンシュユの果実を乾燥したもの。中国や朝鮮に生育しています。
日本には江戸時代中期に薬用植物として朝鮮から種子が持ち込まれました。
薬草酒としても用いられています。
五性:温。五味:辛・酸。帰経:肝・腎。
サンヤク(山薬)
ヤマイモ科ヤマイモ、ナガイモの根茎を乾燥したものです。
「とろろ」でおなじみの山芋のことを漢方では「サンヤク」と呼びます。
五性:平。五味:甘。帰経:脾・胃・肺・腎
タクシャ(沢潟)
サジオモダカの塊茎を乾燥したものです。
草が矢印の形に似て縁起が良いとされ「勝ち草」や「勝軍草」とも呼ばれています。
五性:温。五味:甘。帰経:脾、胃。
ブクリョウ(茯苓)
キノコの1種であるサルノコシカケ科ブクリョウの菌核を乾燥したものです。
薬膳料理にも使用されています。
五性:平。五味:甘・淡。帰経:心・脾・肺・腎。
ボタンピ(牡丹皮)
ボタン科ボタンの根皮を乾燥したものです。
ボタンには鑑賞用と薬用があり、薬用には淡い紅色で花びらが一重のものを用います。
五性:寒。五味:辛・苦。帰経:肝・心・腎。
ケイヒ(桂皮)
クスノキ科ケイの樹皮を乾燥したものです。
香辛料のシナモン(セイロン・ニッケイ)と同じ仲間になります。
中国では古来より「薬物の王」として扱われてきました。
五性:温。五味:辛・甘。帰経:肺・心・膀胱。
ブシ末(附子末)
キンポウゲ科カラトリカブトの塊根を乾燥したものです。
トリカブトといえば有名な毒性植物なので、どこかで耳にしたことのある人も多いでしょう。
生薬に使われているブシ末は、減毒処理が行われていますので安心してください。
五性:熱。五味:辛。帰経:心・脾・腎。
生漢煎®八味地黄丸の価格・値段

どんなに素晴らしい漢方薬でも、続けられないほど高価なものでは意味がありません。
オトクにお買い物したい方のために、生漢煎®八味地黄丸のお買い得情報をお伝えします。
定価は1ヶ月分で5,390円(税込)
生漢煎 八味地黄丸を1箱のみ通常購入する場合、1ヶ月分で5,390円(税込)になります。
さらに、送料が330円(税込)と手数料がかかってしまいます。
トータルすると5,720円となり、毎日続けるにはちょっと高いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。
定期購入なら初回は2,090円(税込)
どうせ生漢煎 八味地黄丸を買うなら、できるだけ安く購入したいと思いませんか。
そこでおすすめしたいのが定期購入コースです。
毎月1箱お届けの定期コースなら、通常価格5,390円(税込)のところ、初回特別価格の2,090円(税込)でお買い求めいただけます!なんと3,630円もおトクです。
つまり毎回おトクに購入できるのです。
さらに、定期コースをお申し込みの方に限り、全国どこでも送料が無料になります。決済手数料も0円です。
「最低何回続けてください」という受け取り回数の縛りもなし
定期コースは安いけれど、途中解約できないのが厄介だと思われがちです。
しかし、生漢煎®八味地黄丸には「最低でも何回続けてください」といった受け取り回数の縛りはありません。
次回お届け日の10営業日前までなら、いつでも好きなときに変更・解約できます。
1回のみでもキャンセルできるので「まずは1回だけ試してみたい」という方も、単品購入ではなく、定期コースをご利用いただくことをおすすめします。
ただし発送の関係で、10営業日前までに以下の番号までご連絡いただく必要があります。
お電話をいただけませんと、次回分が届いてしまうのでご注意ください。
なお、メール・お問い合わせフォームからの解約は承りかねます。
ちなみに休み明けの月曜日や休み前の金曜日の夕方などはお電話が混み合いますので、なるべく避けていただくのが無難です。
・0120-501-068
受付時間:9:00~17:00(※土日祝日を除く)
生漢煎®八味地黄丸の購入方法

生漢煎®八味地黄丸はどこで購入できるのかについてお伝えします。
ご興味をお持ちの方はぜひご覧ください。
公式サイトからが一番お得
八味地黄丸のような医薬品は、薬事法により免許を持たない人は販売できないことになっています。
また、個人で購入したものをフリマサイトなどで第三者に転売することも法律で禁じられています。
もしも見かけたら違法ですので、利用しないでください。
八味地黄丸を初回限定価格で購入できるのはジェイフロンティア株式会社が運営する公式サイト「JFDオンラインショップ」だけです。
価格が一番安いのも公式サイトになるので、あれこれ検索する手間も省けます。
Amazonでは「生漢煎®八味地黄丸」は販売していない
インターネット販売最大級の通販サイトAmazonでも、生漢煎®八味地黄丸の取り扱いはありません。
似たようなものがあったとしても、別のメーカーの商品です。
Amazonで八味地黄丸を探すときには、表面上の価格に惑わされず「1ヶ月分で何円なのか」に注意する必要があります。
とはいえ、直接身体に入れるものですので、やはり品質が高いものを選びたいところ。
当社ではお客様のニーズに応えるべく、一貫製造システムを採用。
製薬会社である「大草薬品株式会社」様の厳しい品質管理・品質保証体制のもと、高度な分析技術を駆使して、より高品質で有効性の高い製品をお届けしています。
※大草薬品株式会社様のWebサイトはこちら
八味地黄丸は、その名が示すように、丸剤で服用するのが最適とされている漢方薬です。
他の剤形よりも長期保存ができ、薬の作用も穏やかで持続力があるといわれています。
しかし、丸剤はエキス剤などと違って、作るのにとても手間がかかり、他の剤形の薬に比べると生産量がわずかなため、今も丸剤を製造している製薬会社は少なくなりました。
しかし当社ではあえて丸剤にこだわって製造を続けています。
丸剤の大きさは直径約5mmの小粒の球形で、独特の香味があり、とても飲みやすいのが特徴です。
大きな錠剤やカプセルを飲むのが苦手な方でも、抵抗なく服用していただけます。
他社の製品と大きさや形状を比べてみてください。
公式サイトでは、品質を重視した漢方薬をお求めやすい価格でご提供しています。
自信を持っておすすめする「生漢煎®八味地黄丸」をこの機会にぜひご活用ください。
